カーソルだけ表示されて背景は真っ黒だったり、一見正常に動くけど数秒〜数分ごとにブラックアウトしたり……。
今回はブラックアウトしたときの原因と対処法をご案内していきます!
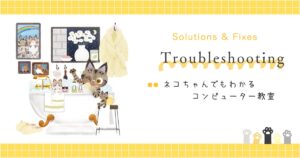
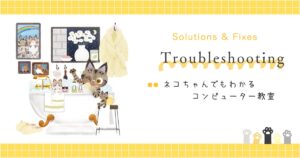
Windowsの場合
電源はついているようだが(カーソルだけ表示され、背景は真っ黒)、アイコンもタスクバーも何も表示されていない状態を「ブラックアウト」といいます。
もし電源がついていない場合は下記の記事を使ってください。
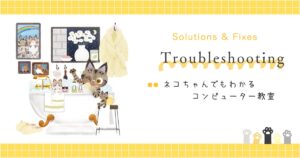
ブルースクリーン(青い画面)になった場合は下記の記事に進んでください。
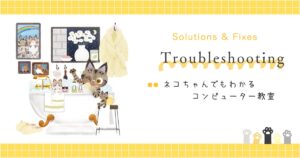
ブラックアウトする主な原因
Windowsのシステム不具合
パソコンの画面が黒くなってしまう原因として、最も多いのはWindowsシステムの不具合です。
まず確認したいのは、前回電源を切った際にWindowsアップデートが実行されていなかったかという点です。
環境によっては、アップデート後にシステムが正常に動作しなくなるケースがあります。
特定のアップデートで不具合が発生した場合、通常はすぐに修正版のアップデートがMicrosoftから配信されます。
そのため、問題解消の更新が提供されるまでしばらく待つ必要がある場合もあります。
また、アップデート以外の要因でWindowsのシステムが破損すると、ブルースクリーン(青いエラー画面)が表示されることがあります。
このブルースクリーンを放置して使用を続けると、システムが起動できなくなり、最終的に黒い画面のまま動かなくなることもあるため、早めの対処が重要です。
電源関連の問題
そもそもパソコンの電源が入らないというケースもよく見られます。
この場合は、ハードウェア、特に電源周りのトラブルである可能性が高いです。
「電源の不具合」と聞くと古いパソコンに多い印象を持たれるかもしれませんが、購入から1年未満の機種でも発生することがあります。
電源に問題があるとパソコンに通電しないため、電源ボタンやアクセスランプ、キーボード・マウスのLEDが点灯しないなどの症状が見られます。
このため、電源トラブルは比較的判断しやすいといえます。
ディスプレイの問題
ディスプレイ自体に不具合がある場合、当然ながら画面は映りません。
オフィスなどで別のディスプレイがある場合は、他のモニターに接続して映るかどうかを確認しましょう。
映像が表示される場合は、ディスプレイ側の問題であることが確定します。
また、デスクトップやマルチディスプレイ環境で作業している場合は、接続ケーブルの不良も考えられます。
ディスプレイの設定確認とあわせて、ケーブルの状態もチェックしてみてください。
なお、キーボードやマウスが点灯しているのに画面が映らない場合は、
ディスプレイの不具合か、あるいはシステム側の問題かを切り分けることが可能です。
どちらに原因があるのか、順に確認していきましょう。
最初に行うこと
再起動
まずは数分〜できれば数十分待ちましょう。
電源はついている、起動はしているという状態なら、バックグラウンドでの処理に時間がかかっていたり、アップデート中であることも多いです。
特にWindowsの更新プログラムが適用中だと、画面が黒いまま長時間動かないように見えることがあります。
ここで強制再起動してしまうとシステムファイルやデータが破損する可能性があるので、まずは待つことが大切です。
※電源ボタンを長押しして強制終了を行うことは推奨できませんので、キーボードで操作できる場合はなるべく避けましょう。
再起動>Ctrl+Alt+Delキーを同時に押す
プログラムがループしたり、処理が止まってしまっている場合は、これらのキーを押すことでシステムが応答し、ディスプレイが表示されることがあります。
もしメニュー画面が表示されたら、「電源」アイコンから再起動を選択します。
また、一度で反応しなくても何度か試すうちにシステムが処理してくれることもありますので、まずはこの方法での再起動を試してください。
どうしても反応しない、再起動できない場合のみ、電源ボタンを長押しして強制終了します。
画面表示を確認する
画面に何が表示されるかを確認するだけでも、問題がハードウェア由来なのか、システム(Windowsシステム)由来なのかを切り分けることができます。
どの段階まで表示されているかを確認し、状況に応じて対応を進めましょう。
メーカーロゴが表示されない場合
パソコンを起動すると、通常は最初にメーカー(例:NEC、DELL、HPなど)のロゴが表示されます。
このロゴはBIOS(Basic Input/Output System)が起動している最中に表示されるものです。
もしこのロゴすら表示されない場合は、BIOS自体が起動していない可能性が高く、メモリ、CPU、またはストレージ(HDD/SSD)などのハードウェア障害が考えられます。
このようなハード面の故障は、部品の交換など修理対応が必要になるケースが多いため、ご自身での対応に不安がある場合は、メーカーや専門業者に依頼するのが安全です。
Windowsロゴが表示されない場合
メーカーのロゴは表示されるのに、Windowsのロゴが出ない場合は、OS(Windowsプログラム)そのものの読み込みに問題が生じています。
まずは再起動を試してみましょう。
改善しない場合は、Windowsの再インストールや修復(スタートアップ修復)を行うことで解決するケースがあります。
もし回復ドライブを作成してある場合はそれを接続して修復作業をすすめることも可能です。
英語のエラーメッセージが表示される場合
起動時に英語のメッセージが表示される場合、それはWindowsではなくBIOSが出している警告であり、多くの場合、ハードウェアや設定の異常を意味しています。
まずは、接続している外部機器(USB、外付けHDD、プリンターなど)をすべて外して起動してみましょう。
それでも改善しない場合は、BIOS/UEFIの設定を初期化(リセット)することで復旧することがあります。
電源・ハードを確認する
電源ケーブル
充電に使用するコンセント、ACアダプター、DCケーブル、DCプラグを確認します。
コンセントが抜けていないか、ACアダプターが異常に熱くなっていないか、ケーブルが断線していないか、またプラグがしっかり差し込まれているかを確認しましょう。
電源タップ(OAタップ)を使用している場合は、一度使用をやめて壁のコンセントに直接つないでみてください。
電源タップが故障していたり、複数の機器を接続していることで 電力供給が不足している可能性もあります。
また、デスクトップパソコンの場合はケース背面の電源ユニットにスイッチがある機種もありますので、それがオフになっていないかも確認しておきましょう。
電源ボタン
経年劣化などで接触が悪くなっている可能性がありますので、一度しっかりと押し込んでみましょう。
バッテリー
ノートパソコンの場合、バッテリーが故障して起動を妨げている可能性もあります。
バッテリーを外せる機種の場合は取り外し、電源ケーブルを接続して起動できるか試してみましょう。
アクセスランプ
パソコンの電源を入れると通常はアクセスランプが点灯します。
機種によっては電源ランプとストレージランプが1つになっていたり、それぞれに分かれている場合もあります。
ストレージランプが点滅するのはデータの読み書きを行なっているときです。
点灯/点滅していれば、パソコンへの電源が供給され、なおかつストレージへのアクセスも正常に行われている状態だとわかります。
一方で、まったく点灯しない場合は電源の供給が行われていない、ストレージへのアクセスが行われていない可能性があります。
※アクセスランプが搭載されていない機種もあります。
ファンの音
電源をオンにしたときに、ファンの回る音がするか確認してみましょう。
もしファンが動作しているなら電気の供給はされているということになります。
そうなると電源以外の問題(マザーボードやメモリ、HDDやSSD、ディスプレイなど)を探す必要が出てきます。
また、コンコン、カンカン、カチカチなどの異音がする場合は物理的に損傷している可能性がありますので、電源を入れるのはやめて修理に出すことを検討してください。
※ただし最近のノートパソコンや静音設計モデルでは、起動直後や低負荷時にファンが停止していることもありますので、あくまでも目安としてください。
温度
パソコンのパーツの中には高温になってしまうものがあり、通常は冷却ファンで熱を抑えるのですが、重い作業で負荷をかけすぎたり、大きなデータを取り扱ったり、部屋の中が熱くなりすぎていたりすることが原因で冷やすのが追いつかなくなってしまうことがあります。
そうするとパソコンは故障してしまうのを防ぐために動作を一時的に停止するようになっています。
パソコンを触って熱くなっていたり、ファンが高速で回る音が止まらない場合はできるだけ部屋を涼しくし、しばらく放置してください。
また、パソコンは温度を下げるために空気を取り込む必要があるのでパソコンに布を掛けていたり、下になにか敷いていたり、壁に近づけすぎて吸気口を塞いでいたりする場合はすべて取り除くようにしましょう。
帯電(放電する)
電気が溜まってしまうことを帯電といいますが、パソコン内部のパーツに電気が帯電してしまうことがあります。
帯電するとパソコンの電源が急に落ちたり、起動できなくなったりします。
その場合は電源ケーブル、すべての周辺機器(マウスやキーボード、ディスプレイも含む)、ノートパソコンの場合はバッテリーもすべて取り外した状態で10〜15分ほど放置しましょう
機種によってはすべて取り外した状態にしたあと電源ボタンを15秒間長押して残留電荷をコンデンサーから放電します。
※この方法はバッテリーがまったく充電できなくなってしまったときにも有効です。
埃
埃が吸気口や冷却ファンの羽に溜まると、ファンの動きが妨げられ、内部が高温になり、結果的にパソコンの動作が停止することにつながってしまいます。
ケースを開けて掃除するのが難しい場合も、まずは外側の吸気口に詰まった埃をエアダスターなどを使って取り除きましょう。
掃除を行う際は必ず電源を切り、電源ケーブルも抜いた状態で行い、静電気が発生しやすい環境での作業は避けるようにしてください。
ディスプレイ/モニター
特にデスクトップパソコンの場合、実際にはパソコンの電源は入っており、ディスプレイの電源が切れていただけだったというケースがよくあります。
ディスプレイの電源スイッチがオフになっていないか、背面の電源プラグやコンセントが抜けていないか、HDMIなどの映像ケーブルが外れていないかを確認してみましょう。
もしモニターとパソコンの電源ランプはつくのに表示はされない、という場合には、HDMIなどの映像ケーブルをテレビに繋いでみます。
※ケーブルを抜き差しする際は、念のため電源を切ってから行いましょう。
そこでグラフィックドライバーのアンインストールし、再起動を試してからもう一度モニターに繋ぎ直してみてください。
周辺機器を外す
外付けハードディスク(SSD/HDD)、USBメモリ、USBヘッドセット、マウス、プリンターなどの周辺機器が原因でエラーが起こる場合もあります。
まずは、これらを一旦すべて取り外してからパソコンを再起動し、動作を確認します。
ブラックアウトした場合は、すぐに電源を切らず、しばらく待って自動的に再起動されるか確認し、もしエラーコード(停止コード)が表示されたら控えておきましょう。
外付け機器を取り外した状態で正常に起動できた場合は、接続していた機器やそのドライバーに問題がある可能性があります。
電源ケーブルやバッテリーの状態にも注意しながら、必ず電源を切ってから作業を行いましょう。
次に、それぞれの外付け機器のドライバーが最新かどうかを確認します。古い場合は最新のドライバーをインストールしてから、1台ずつ接続して動作を確認してください。
特定の機器を接続したときに再びエラーが発生する場合は、その機器のドライバーがお使いのパソコンと互換性がないか、機器自体が故障している可能性があります。
このような場合は、使用を中止し、メーカーに相談することをおすすめします。
また、問題のある機器を接続したまま再起動を繰り返したり、通電を続けると状態が悪化し、最悪の場合データが復旧できなくなることもありますので早めに対処しましょう。
ハード構成の点検
BIOSの設定を見直す
BIOSの設定に誤りがあると、ハードウェアが正常に認識されず不具合が発生することがあります。
OSの読み込みやハードウェアの制御を行っているBIOS(Basic Input/Output System)に異常が起きるとエラーが発生します。
BIOS設定を初期化または正しい値に変更して再起動を試みます。
パソコンの電源を入れる>F2キー(すぐに開かない場合は連打する)>「BIOSセットアップユーティリティ」>矢印キーを使い、「Boot」>Enterキー>「Boot Device Priority」>Enterキー>「1st Boot Device」>Enterキー>ドライブ(Windowsがインストールされているもの)を選択する>Enterキー>矢印キーで「Save Changes and Reset」を選択>Enterキー
※初期化することもできますがデータ消失や機器の破損などのリスクがあるため推奨はしておりません。
メモリーを点検する
メモリーが正しく差し込まれていない場合や接触不良がある場合、エラーが発生することがあります。
一度メモリーを取り外し、差し直してから再起動します。それでも解消しない場合はメモリー自体の交換が必要です。
メモリを差し込む際は、まず静電気対策を行うことが基本で、作業前に金属部分に触れて放電し、部品を傷めないようにします。
メモリを差すときは、スロットの溝とメモリの切り欠きを正しく合わせ、かたくて入りにくい場合は無理に押し込まずに一度抜いて向きや位置を確認します。
押し込みは上からだけでなく左右からも力をかけ、スロットの溝を押し広げるようにします。
徐々に力を加え、最後は一気に押し込むと「パチン」と音がしてツメがはまりますので、この音が装着完了の目安です。
前後に揺らしたり、こじ入れたりするのは絶対に厳禁、部品が樹脂製のため、破損の原因になります。
斜めに差し込むと抜けなくなる場合もあるため、左右が均等に入っているか確認してから押し込みます。
片側のツメが少し浮いている場合でも動作する場合がありますが、それでも気づいたときに確実にはめ直すことが大切です。
タスクバーの検索ウィンドウに「メモリ」>「Windows メモリ診断」を選択>「今すぐ再起動して問題の有無を確認する」>再起動の途中でメモリ診断がはじまったら、F1キー>矢印キーで操作し、「テストミックス」の項目で「標準」を選択>Tabキー>「パスカウント」選択>回数は5を入力>F10キーを押す>診断終了を待つ>メモリエラーが検出された場合は、メモリモジュールの故障の可能性があるため、交換または修理を検討する
HDDやSSDを交換する
内部ストレージの故障や破損が原因の場合、修理または交換が必要です。ディスクエラーが頻発する場合は、早めに対処しましょう。
Windowsが起動する場合の対処
セーフモードで起動する
セーフモードでは、Windowsが最低限の機能だけで起動するため、問題のあるドライバーやプログラムを回避できることがあります。
「自動修復」の画面で、「詳細オプション」>「オプションの選択」にある「トラブルシューティング」>「詳細オプション」を選択し、画面遷移後に「スタートアップ設定」>画面右下に表示される「再起動」>「オプションを選択するには、番号を押してください」と表示されたら、キーボードの4キーかF4キーを押す
ドライバーを元に戻す/アンインストールする
直近で更新されたデバイスドライバーが原因であることが多くあります。
スタートボタン右クリック>「デバイスマネージャー」>該当するデバイスを選択して右クリック>「プロパティ」>「ドライバー」タブ>「ドライバーを元に戻す」>「OK」
またはアンインストールします。
スタートボタン右クリック>「デバイスマネージャー」>該当するデバイスを選択して右クリック>「ドライバをアンインストール」>「アンインストール」※「このデバイスのドライバーソフトウェアを削除します」にはチェックを入れません
特にグラフィックボード、ストレージ、ネットワークアダプターは影響が大きく、症状としては再起動を繰り返す、パソコンが起動しない、ブラックアウトする、ブルースクリーンが一瞬で消えるなどが見られます。
作業後は自動更新を一時的に停止して再発を防ぎましょう。
セーフモードが安定して動作する場合は、セーフモードで実行すると失敗が減ります。
「自動修復」の画面で、「詳細オプション」>「オプションの選択」にある「トラブルシューティング」>「詳細オプション」を選択し、画面遷移後に「スタートアップ設定」>画面右下に表示される「再起動」>「オプションを選択するには、番号を押してください」と表示されたら、キーボードの4キーかF4キーを押す
代表的なデバイスと症状の関係は以下の通りです。
グラフィック:画面の点滅や停止コードVIDEO系が出る場合は、ドライバーのクリーンインストールも検討します。
※グラフィックドライバーはメーカー提供ユーティリティでクリーンインストールを行うと、残存設定が原因の不具合を除去できます。
ストレージまたはコントローラー:起動しない、停止コードINACCESSIBLE_BOOT_DEVICEが出る場合は、SATAまたはNVMe設定を確認します。
ネットワーク:起動直後にブルースクリーンが頻発する場合は、省電力設定を無効化します。
※特殊なケース出ない限りはBIOSのアップデートを行うと解消することが多いため、定期保守として行うのが理想的です。
更新プログラムをアンインストールする
Windowsの更新プログラムが原因でエラーが起きる場合があります。
特にWindows Updateの適用直後に不具合が発生した場合は、更新プログラムを一時的にアンインストールし、アップデート前の状態に戻すことで問題が解消することがあります。
特定のアップデートによって不具合が発生した場合は、通常数日以内に修正版のアップデートがMicrosoftから配信されます。
そのため、問題解消の更新が提供されるまで待つ必要が生じることもあります。
また、アップデート以外の原因でWindowsのシステムが破損し、不具合が発生するケースもあります。
その際には「ブルースクリーン」と呼ばれる青い画面が表示されることが多く、ブルースクリーンを放置したまま使用を続けると、最悪の場合システムが起動しなくなり、ブラックアウトしたまま動かなくなることもあります。
そのため、早めに対処することが非常に重要です。
作業はセーフモードで行い、最近インストールされた更新プログラムをアンインストールしてから再起動します。
問題が解消したら、新しいバージョンの更新を待って再インストールするのが安全です。
ただし、内蔵HDD/SSDの認識異常や動作の遅延がある場合、機器の経年劣化や故障の可能性もあるため、そのような症状が見られるときはアンインストール作業を避けてください。
状態が悪化し、データの破損や起動不能に陥るおそれがあります。
また、Windows Updateで配信される更新プログラムはセキュリティ修正や不具合改善を目的としているため、むやみに削除すると別のトラブルや脆弱性が生じることがあります。
したがって、特定のプログラムやハードウェアの導入後にブラックアウトが発生した場合など、原因をある程度特定できるケースに限定してアンインストールを行うようにしましょう。
アンインストールを実施しても改善しない場合は、「システムの復元」でブラックアウト発生前の状態に戻す方法も有効です。
操作に不安を感じる場合や、保存データが重要な場合は、無理に作業を進めずプロのデータ復旧・修理業者に相談することをおすすめします。
ウイルスを診断・駆除する
ウイルス感染によってシステムファイルが破損し、エラーが発生することがあります。
ウイルス対策ソフトでフルスキャンと駆除を行い、感染が確認された場合はネットワークを切断して情報漏えいを防ぎます。
セーフモードで起動後に行いましょう。
「自動修復」の画面で、「詳細オプション」>「オプションの選択」にある「トラブルシューティング」>「詳細オプション」を選択し、画面遷移後に「スタートアップ設定」>画面右下に表示される「再起動」>「オプションを選択するには、番号を押してください」と表示されたら、キーボードの4キーかF4キーを押す
システムを復元する
復元ポイントを設定している場合、システムを正常に動作していた時点に戻すことができます。
直近の更新や設定変更によるトラブルを解消するのに最も有効な手段です。
※システムの復元は、ドライバーやアプリ、レジストリなどのシステム構成を過去の状態に戻す機能ですので、通常、文書や写真などの個人データは削除されませんが、復元ポイント以降にインストールしたアプリやドライバーは無効化・削除されることがあります。
パソコンの強制終了と起動を複数回繰り返す>「スタートアップ修復」を起動>「自動修復」画面>「詳細オプション」>「システムの復元」>画面の指示通りに進める
もし回復ドライブを作成してある場合はそれを接続して修復作業をすすめることも可能です。
システムの修復(コマンド)
DISMコマンドを実行する
DISMコマンドはシステムイメージの破損を修復するツールです。
エラー画面の「トラブルシューティング」>「詳細オプション」の中にある「コマンドプロンプト」>「コマンドプロンプト」>DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealthと入力し、コマンドを実行する
システムファイルチェッカーを実行する
システムファイルの整合性を確認し、不適切なものを正しいバージョンに置き換えて破損したファイルを修復する方法です。
タスクバーの検索ボックスに「command prompt」と入力>「コマンドプロンプト(デスクトップ アプリ)」 を右クリックもしくは長押し>「管理者として実行」>「はい」>DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealthと入力>Enterキー>「操作が正常に完了しました」とメッセージが表示される>sfc/scannowと入力>Enterキー>「検証 100% 完了」と表示される>exitと入力>Enterキーを押して完了
スタートアップ修復を行う
スタートアップ修復は起動に関するトラブルを自動で検出・修復する機能です。
自動的に起動しない場合は詳細オプションから手動で実行できます。ただし繰り返しの利用はシステムに負荷をかけるため、必要な場合に限定します。
もし回復ドライブを作成してある場合はそれを接続して修復作業をすすめることも可能です。
最終手段
パソコンを初期化する
上記の方法でも解決しない場合は、パソコンの初期化を検討します。
初期化を行うと設定や保存データが全て消去されるため、事前にバックアップを取ることが重要です。
補足:グラフィックアクセラレーションをOFFにする
もしブラックアウトするのがGoogle Chromeの使用時のみの場合は有効です。
Chrome>右上「︙」>「設定」>「システム」>「グラフィック アクセラレーションが使用可能な場合は使用する」をOFFにする>「再起動」をクリックする
Chromeが一度閉じられ、再度開いたら完了です。
Macの場合
突然、Macが起動しなくなり、画面が真っ黒なままでカーソル(マウスポインタ)だけが表示される状態になったことはありませんか。
このような現象は、一般的に「ブラックアウト」と呼ばれ、Macでは決して珍しいものではありません。
電源は入っており、ファンの音や起動音から本体が動作していることは確認できるのに、画面には何も表示されず、カーソルだけが動く――。
場合によっては、カーソルが点滅しているだけで一切の操作を受け付けないこともあります。
このような状態の原因には、ソフトウェア的な要因とハードウェア的な要因の両方が考えられます。
最初に行うこと
ロック画面を解除する
実際にはMacがロック画面(ログイン画面)で待機しているものの映像だけが表示されていない場合があります。
キーボードでMacのログインパスワードを入力する>Enter /returnキーを押す
正しくパスワードが入力されればログインが完了し、通常のデスクトップ画面が表示される可能性があります。
再起動する
Macを強制終了して再起動してみましょう。
電源ボタン(またはTouch IDボタン)を約10秒間長押しして電源を切り、
その後、再度電源ボタンを押して起動し直します。
一時的なシステムの不具合であれば、再起動によって改善するケースがほとんどです。
原因が特定できない場合でも、システムを一度リセットすることで正常に起動するかを確認してみてください。
軽く触れるだけでは反応しないため、しっかりと長押しすることで強制終了を行ってください。
電源・ハードの基本確認
電源コード
充電に使用するコンセント、ACアダプター、電源コード、USB-C/MagSafe(USB-C)アダプタを確認します。
コンセントが抜けていないか、ACアダプターが異常に熱くなっていないか、ケーブルが断線していないか、またプラグがしっかり差し込まれているかを確認しましょう。
電源タップ(OAタップ)を使用している場合は、一度使用をやめて壁のコンセントに直接つないでみてください。
電源タップが故障していたり、複数の機器を接続していることで 電力供給が不足している可能性もあります。
また、デスクトップパソコンの場合はケース背面の電源ユニットにスイッチがある機種もありますので、それがオフになっていないかも確認しておきましょう。
電源ボタン
経年劣化などで接触が悪くなっている可能性がありますので、一度しっかりと押し込んでみましょう。
バッテリー
ノートパソコンの場合、バッテリーが故障して起動を妨げている可能性もあります。
バッテリーを外せる機種の場合は取り外し、電源コードを接続して起動できるか試してみましょう。
ファンの音
電源をオンにしたときに、ファンの回る音がするか確認してみましょう。
もしファンが動作しているなら電気の供給はされているということになります。
※Macの場合はほぼ無音/無風か、起動直後に瞬間回転するだけの場合が多いです。
そうなると電源以外の問題(マザーボードやメモリ、HDDやSSD、ディスプレイなど)を探す必要が出てきます。
また、コンコン、カンカン、カチカチなどの異音がする場合は物理的に損傷している可能性がありますので、電源を入れるのはやめて修理に出すことを検討してください。
※ただし最近のノートパソコンや静音設計モデルでは、起動直後や低負荷時にファンが停止していることもありますので、あくまでも目安としてください。
ディスプレイ
特にデスクトップパソコンの場合、実際にはパソコンの電源は入っており、ディスプレイの電源が切れていただけだったというケースがよくあります。
ディスプレイの電源スイッチがオフになっていないか、背面の電源プラグやコンセントが抜けていないか、HDMIなどの映像ケーブルが外れていないかを確認してみましょう。
周辺機器を外す
周辺機器は一度すべて外しておきましょう。
外部機器の電力消費が大きすぎる、接続機器が多すぎて干渉している、ドライバーが不具合を引き起こしているなど、原因はさまざまあります。
ひとまずマウス、キーボード、ディスプレイなどの最低限だけを残します。
外部スピーカー、サブディスプレイ、ヘッドセット、マイク、カメラ、プリンター、モバイルデバイスなど操作に必須ではないものは外します。
USB拡張ハブを使っている場合はハブごとすべて外します。
さらに外付けのHDD、SSDを使用している場合はそれも外しておきます。
またBluetooth機器も一度機器側で接続を解除するか、電源を切っておくのをおすすめします。
※機器を取り付けるときはひとつずつ試し、どれが起動を妨げているのか確認しましょう。
温度
パソコンのパーツの中には高温になってしまうものがあり、通常は冷却ファンで熱を抑えるのですが、重い作業で負荷をかけすぎたり、大きなデータを取り扱ったり、部屋の中が熱くなりすぎていたりすることが原因で冷やすのが追いつかなくなってしまうことがあります。
そうするとパソコンは故障してしまうのを防ぐために動作を一時的に停止するようになっています。
パソコンを触って熱くなっていたり、ファンが高速で回る音が止まらない場合はできるだけ部屋を涼しくし、しばらく放置してください。
また、パソコンは温度を下げるために空気を取り込む必要があるのでパソコンに布を掛けていたり、下になにか敷いていたり、壁に近づけすぎて吸気口を塞いでいたりする場合はすべて取り除くようにしましょう。
帯電(放電する)
電気が溜まってしまうことを帯電といいますが、パソコン内部のパーツに電気が帯電してしまうことがあります。
帯電するとパソコンの電源が急に落ちたり、起動できなくなったりします。
その場合は電源コード、すべての周辺機器(マウスやキーボード、ディスプレイも含む)、ノートパソコンの場合はバッテリーもすべて取り外した状態で10〜15分ほど放置しましょう
機種によってはすべて取り外した状態にしたあと電源ボタンを15秒間長押して残留電荷をコンデンサーから放電します。
埃
埃が吸気口や冷却ファンの羽に溜まると、ファンの動きが妨げられ、内部が高温になり、結果的にパソコンの動作が停止することにつながってしまいます。
ケースを開けて掃除するのが難しい場合も、まずは外側の吸気口に詰まった埃をエアダスターなどを使って取り除きましょう。
掃除を行う際は必ず電源を切り、電源コードも抜いた状態で行い、静電気が発生しやすい環境での作業は避けるようにしてください。
システムのリセット
SMCリセット
Intel搭載モデルの場合は有効です。
Appleシリコン搭載のMacの場合は再起動するか、シャットダウンして再度起動するだけで自動的にSMCがリセットされるので特別な操作は必要ありません。
MacBook Pro (2021 年以降に発売されたモデルおよび MacBook Pro (13-inch, M1, 2020))
MacBook Air (2022 年以降に発売されたモデルおよび MacBook Air (M1, 2020))
iMac (2021 年以降に発売されたモデル)
Mac mini (2020年以降に発売されたモデル)
Mac Studio (2022 年以降に発売されたモデル)
Mac Pro (2023 年に発売されたモデル)
Apple T2セキュリティチップ搭載のノートブック型
MacBook Pro (2018 ~ 2020 年に発売されたモデル)、MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) を除く
MacBook Air (2018 ~ 2020 年に発売されたモデル)、MacBook Air (M1, 2020) を除く
iMac (Retina 5K、27 インチ、2020) と iMac Pro
Mac mini (2018)
Mac Pro (2019 年に発売されたモデル)
電源が落ちている状態でControl ^(キーボードの左側)+option⌥(alt)(キーボードの左側)+shift⇧(キーボードの右側)と電源ボタンの4つを7秒以上長押しします。
※左右の指定があります。
もし途中で起動した場合、再度電源が消えるまで長押しを続けてください。
さらに7秒長押ししてから指を離し、電源を入れます。
T2 チップを搭載したデスクトップ型
MacBook Pro (2018 ~ 2020 年に発売されたモデル)、MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) を除く
MacBook Air (2018 ~ 2020 年に発売されたモデル)、MacBook Air (M1, 2020) を除く
iMac (Retina 5K、27 インチ、2020) と iMac Pro
Mac mini (2018)
Mac Pro (2019 年に発売されたモデル)
電源が落ちている状態で、電源コードも外します。
15秒待って電源コードを再度つなぎ、5秒待ってから電源を入れます。
AppleシリコンもT2チップも搭載していないノートブック型
※2017年以前のモデルにはAppleシリコンもT2チップも搭載されていません(一部モデル除く)。
電源が落ちている状態でControl ^(キーボードの左側)+option⌥(alt)(キーボードの左側)+shift⇧(キーボードの左側)と電源ボタンの4つを10秒以上長押しします。
※左右の指定があります。
もし途中で起動した場合、再度電源が消えるまで長押しを続けてください。
さらに10秒長押ししてから指を離し、電源を入れます。
AppleシリコンもT2チップも搭載していないデスクトップ型
※2017年以前のモデルにはAppleシリコンもT2チップも搭載されていません(一部モデル除く)。
電源が落ちている状態で、電源コードも外します。
15秒待って電源コードを再度つなぎ、5秒待ってから電源を入れます。
NVRAM/PRAMリセット
Apple シリコン搭載のMacの場合
Macの電源を入れ、Macが起動している間、そのまま電源ボタンを押し続ける>起動オプションの画面が表示されたら、電源ボタンから指を放す>起動オプションの画面には、起動ディスクと、「オプション」というラベルの付いたギアマークのアイコンが表示される>この画面から、別のディスクから起動する、セーフモードで起動する、macOS復旧を使うなどの操作が可能
MacBook Pro (2021 年以降に発売されたモデルおよび MacBook Pro (13-inch, M1, 2020))
MacBook Air (2022 年以降に発売されたモデルおよび MacBook Air (M1, 2020))
iMac (2021 年以降に発売されたモデル)
Mac mini (2020年以降に発売されたモデル)
Mac Studio (2022 年以降に発売されたモデル)
Mac Pro (2023 年に発売されたモデル)
MacにAppleシリコンが搭載されていない場合は、Intel搭載モデルです。
Intel搭載のMacの場合
キーコンビネーションを使うときは、組み合わせるすべてのキーを同時に押し続けてください。
Macの再起動時にキーを押し損ねた場合は、まずMacをシステム終了します(システム終了できない場合は、電源ボタンを10秒ほど押し続けます)。
電源が切れたら再び電源ボタンを押してMacを起動し、キーコンビネーションを長押しします。
※起動時にキーボードが認識されるまで数秒かかることがありますが、キーボードのライトが点滅してからキーを押すと、認識されやすくなります。
※ワイヤレスキーボードを使用している場合は、可能であればMacに直接接続するか、内蔵キーボードや有線キーボードを使ってください(Windows用のキーボードを使用している場合は、Mac用のキーボードを試してください)。
Macにファームウェアパスワードが設定されていると、一部のキーコンビネーションは使えませんので、その場合は、まずファームウェアパスワードを解除してください。
※Boot Campを使ってWindowsから起動している場合は、システム環境設定の起動ディスクでmacOSを選び、システムを終了または再起動してからもう一度試します。
Intel 搭載 Mac 向けのキーコンビネーション
command⌘+Rキー>macOS復旧システムから起動する
option⌥+command⌘+Rキー/またはshift⇧+option⌥+command⌘+Rキー>インターネット経由でmacOS復旧を起動する
※インストールされるmacOSのバージョンは押すキーの組み合わせによって異なります。
option⌥(またはaltキー)>「Startup Manager」を起動し、別の起動ディスクやボリュームを選択できる
option⌥+command⌘+P+Rキー>NVRAMまたはPRAMをリセットできる
shift⇧キー>セーフモードで起動する
Dキー:Apple Diagnosticsを起動、option⌥+Dキーを使うとインターネット経由で起動する
Nキー>NetBootサーバから起動する>option⌥+Nキーを押すとサーバ上のデフォルトの起動イメージを使用する
command⌘+Sキー>シングルユーザモードで起動、macOS Mojave以降では無効になる
Tキー>ターゲットディスクモードで起動する
command⌘+Vキー>verboseモードで起動する
取り出し (⏏) キー(あるいははF12キー)/またはマウスボタン/またはトラックパッドボタン>リムーバブルメディアを取り出す
ソフトウェア的対処
macOS復旧から起動する
Apple シリコン搭載のMacの場合
MacBook Pro (2021 年以降に発売されたモデルおよび MacBook Pro (13-inch, M1, 2020))
MacBook Air (2022 年以降に発売されたモデルおよび MacBook Air (M1, 2020))
iMac (2021 年以降に発売されたモデル)
Mac mini (2020年以降に発売されたモデル)
Mac Studio (2022 年以降に発売されたモデル)
Mac Pro (2023 年に発売されたモデル)
Macの電源が切れていることを確認(通常通りにシステム終了できない場合は、Macの電源ボタンを10秒ほど、電源が切れるまで押し続ける)>電源ボタンを再び長押し>電源ボタンを押し続けると、Macの電源が入り、起動オプションが読み込まれる>「起動オプションを読み込み中」というメッセージ、または「オプション」アイコンが表示されたら、電源ボタンを放す>「オプション」をクリックし、その下に表示される「続ける」ボタンをクリックする>復旧するボリュームを選択するよう求められた場合は、起動ディスク(Macintosh HDなど)を選択する>「次へ」をクリック>ユーザを選択し、「次へ」をクリック>そのユーザがこのMacにログインするために使っているパスワードを入力する>Macが復旧から正常に起動するとユーティリティがウインドウに表示される>画面上部のメニューバーからは、ターミナルなどのほかのユーティリティを利用できるので、いずれかのユーティリティを実行するか、Appleメニュー()から「再起動」または「システム終了」を選択して復旧を終了する
①Time Machineから復元
②macOSを再インストール
③ディスクユーティリティ(起動ディスクを修復または消去するときに使用)
macOS復旧から起動できない場合(Appleシリコン搭載モデルのMac)
Macの起動プロセスが完了せず、起動中に画面に何も表示されなかったり、円で囲まれた感嘆符やその他の画面が表示される場合はNVRAMをリセット、macOS再インストールなど手順を一からやり直してください。
Intel搭載モデルのMacの場合
お使いのMacがAppleシリコン搭載モデルでない場合は、Intel搭載モデルです。
※Macの種類を特定できない場合は、Appleシリコン搭載モデルのMacの手順を試してみても大丈夫です。
Macの電源が切れていることを確認(通常通りにシステム終了できない場合は、Macの電源ボタンを10秒ほど、電源が切れるまで押し続ける)>電源ボタンを押して放し、Macが起動したらすぐにキーボードのcommand⌘+Rキーを長押しして、Appleロゴまたは回転する地球儀が表示されるまで押し続ける>ネットワークを選択するよう求められた場合は、Wi-Fiメニュー からネットワークを選択するか、ネットワークケーブルを接続する>復旧するボリュームを選択するよう求められた場合は、起動ディスク(Macintosh HDなど)を選択する>「次へ」をクリック>ユーザを選択するよう求められた場合は、ユーザを選択し、「次へ」をクリック>そのユーザがこのMacにログインするために使っているパスワードを入力する>Macが復旧から正常に起動すると、ユーティリティがウインドウに表示される(画面上部のメニューバーからは、ターミナルなどのほかのユーティリティを利用できる)>いずれかのユーティリティを実行するか、Appleメニュー()から「再起動」または「システム終了」を選択して復旧を終了する
①Time Machineから復元
②macOSを再インストール
③ディスクユーティリティ(起動ディスクを修復または消去するときに使用)
macOS復旧から起動できない場合(Intel搭載モデルのMac)
起動時に押しているキーが、Macによって確実に認識されるように、以下の点を確認してください。
Macノートブックをお使いの場合は、外付けキーボードではなく内蔵キーボードを使ってください。
外付けキーボードをお使いの場合は、起動時にキーボードがMacに認識されるまでの時間を考慮し、数秒間待ってからキーを押してみてください。
一部のキーボードには、キーボードを使う準備が整うと短く点滅するステータスランプが付いています。
キーボードをワイヤレスでお使いの場合は、可能であればキーボードをMacに接続するか、有線キーボードを使ってみてください。
Windowsパソコン用のキーボード(Windowsのロゴが付いたものなど)をお使いの場合は、Mac用のキーボードを使ってみてください。
Macを内蔵の復旧システムから起動できないときは、インターネット経由で復旧から起動する仕組みになっており、回転する地球儀が自動的に表示されます。
または、起動時にcommand⌘+Rキーではなく、option⌥+command⌘+Rキー/またはshift⇧+option⌥+command⌘+Rキーの組み合わせを押して、強制的にインターネット復旧を実行することもできます(組み合わせによって、復旧からmacOSを再インストールする際に提供されるmacOSのバージョンが異なります)。
※回転する地球儀と警告マーク(感嘆符)が表示された場合は、インターネット復旧からの起動が失敗したことを示しています。
このとき表示される画面と番号付きのエラーの大半は、ネットワークまたはインターネット接続の問題に関連しています。以下の解決法で対処してみてください。
Macがインターネットに接続されていることを確認、また、Wi-Fiの代わりにEthernetを使うなど、別の手段で接続すると問題が解決する場合があります。
command⌘+Rキー/option⌥+command⌘+Rキー/shift⇧+option⌥+command⌘+Rキーの組み合わせを試してください。
別のネットワークを試してください。
一時的な問題の場合は、時間をおいて再度試してください。
Macの起動プロセスが完了せず、起動中に画面に何も表示されなかったり、感嘆符やその他の画面が表示されたりする場合はNVRAMをリセット、macOS再インストールなど手順を一からやり直してください。
Microsoft WindowsからBoot CampでMacを起動するよう設定してある場合は、macOSから起動し、システムを終了してからもう一度試してください。
Macの起動時にエラー-1008Fが表示される/地球儀に感嘆符が表示される場合、Macがインターネット経由でmacOS復旧から起動しようとして、できなかった状況です。
スマホやタブレット経由でアクティベーションロックを無効にし、macOS復旧の手順を行ってください(復旧が完了したらアクティベーションロックを有効に戻すことができます)。
また、macOS復旧から起動する際、起動時には、command⌘+Rキーやshift⇧+option⌥+command⌘+Rキーではなく、option⌥+command⌘+Rキーキーを使用してください。
改善しないとき
上記の対処法をすべて試しても改善しない場合は、システム障害かハードウェア故障の可能性が高いです。
AppleシリコンやT2チップ搭載Macでファームウェアの不具合が原因となっている場合はApple Configuratorを使ったDFUモードでの復元が必要ですが、その際は無理をせずApple Storeへ行くか、Appleのカスタマーへ問い合わせましょう。
補足:グラフィックアクセラレーションをOFFにする
もしブラックアウトするのがGoogle Chromeの使用時のみの場合は有効です。
Chrome>右上「︙」>「設定」>「システム」>「グラフィック アクセラレーションが使用可能な場合は使用する」をOFFにする>「再起動」をクリックする
Chromeが一度閉じられ、再度開いたら完了です。
最後に
もし自分でできる範囲の対処をしても解決しない場合は、無理にケースを開けたり、分解したりせずに修理を依頼することをおすすめします!
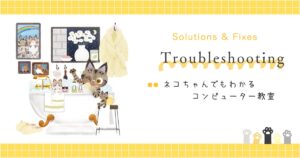
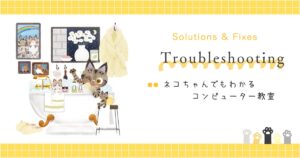
.png)




コメント